スタートアップ
シード期における資金調達
皆さんこんにちは。XP法律事務所です。成長段階にあるスタートアップ企業においては、ビジネスモデルの検討、役員の選任、人材確保等のクリアすべき課題が多くありますが、事業拡大のために必要な資金の調達は特に重要な問題です。スタートアップ企業の成長過程には、シード、アーリー、ミドル、レイターとあり、成長段階に応じた適切な資金調達が不可欠です。本稿では、会社設立前後のシード期に焦点を当てて、具体的な方法や法的な課題についてご説明します。
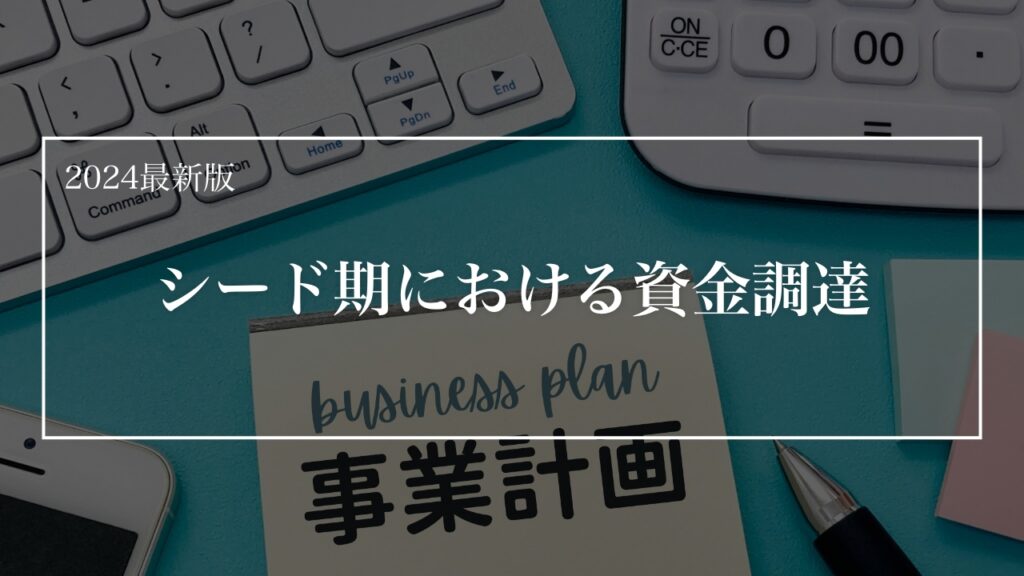
arrow_drop_down 目次
1. はじめに
皆さんこんにちは。XP法律事務所です。
成長段階にあるスタートアップ企業においては、ビジネスモデルの検討、役員の選任、人材確保等のクリアすべき課題が多くありますが、事業拡大のために必要な資金の調達は特に重要な問題です。
スタートアップ企業の成長過程には、シード、アーリー、ミドル、レイターとあり、成長段階に応じた適切な資金調達が不可欠です。
本稿では、会社設立前後のシード期に焦点を当てて、具体的な方法や法的な課題についてご説明します。
2. シード期の位置付けと資金調達
スタートアップ企業のシード期は、時期としては会社設立の前後の時点であり、起業家に事業のアイデアはありながらも、そのアイデアが具体的な製品やサービスとして実現されていない段階です。
そのため、事業のアイデアを製品やサービスという形で具現化するために、設備維持、人材確保等にあてる資金が必要となります。
もっとも、会社創業者の自己資金や、会社設立直後の売上ではこのような資金を賄うには不十分であるため、他人の資金を利用する資金調達が重要な意味を持ちます。
企業の資金調達の手法は大きく、デットファイナンス(融資)とエクイティファイナンス(投資)とに分かれます。
さらに、エクイティファイナンスについては、普通株式、みなし優先株式、有償新株予約権、有償新株予約権、新株予約権付社債などの手法があるため、以下ではそれぞれの特徴・資金調達先等について詳細をご説明いたします。
3. デットファイナンス
(1)デットファイナンスの概要
デットファイナンスとは負債による資金調達のことで、企業は、元本・利子について返済義務を負います。
投資家に対する社債の発行、銀行からの借り入れなどがその具体例です。
企業には返済義務がある反面、債権者には議決権はなく、基本的に会社の経営に関与することはできないのが後述するエクイティファイナンスとの大きな違いです。
(2)デットファイナンスのメリット
資金調達を行う企業におけるデットファイナンスのメリットとしては、企業の業績がどれだけ良くても、返済すべき金額が契約に定められた元本及び利子に限定される点が挙げられます。
債権者の側から見れば、ローリスク・ローリターンな投資ということができます。
(3)デットファイナンスのデメリット
これの裏返しとして、企業の業績が悪い場合でも返済の義務は基本的に変わりませんので、返済が負担となることが企業にとってのデメリットとなります。
(4)資金調達先
デットファイナンスによる一般的な資金調達先は銀行等の金融機関です。
しかし、通常の金融機関からの借り入れに際しては、担保・保証人の提供や金利の支払いが必要となる点が企業にとっての負担となりえます。
そこで、シード期のスタートアップ企業としては、公的金融機関からの借り入れ、制度融資等の利用を検討することが有効です。
A)公的金融機関からの融資
公的金融機関は中小企業やスタートアップ企業を支援するための融資制度を運用しており、シード期のスタートアップ企業としてはこれを利用することでより効率的な資金調達が可能となります。
たとえば、日本政策金融公庫の場合、新事業育成資金、スタートアップ支援資金、新創業融資制度、新規開業資金といった融資制度を提供しています。
事業内容や、設立からの期間、融資限度額等の一定の要件を満たす必要はありますが、これらを利用することで、低金利での借り入れや、無担保・無保証での借り入れができる可能性があります。
B)信用保証協会・地方自治体による制度融資
制度融資とは、指定金融機関からの借り入れに際し、都道府県や市町村等の地方自治体が利息を一部負担し、さらに信用保証協会に債務を保証してもらうというものです。
信用保証協会の保証により融資が受けやすくなる点、企業が支払う利息が低額で済む点で、シード期のスタートアップにとって検討すべき資金調達方法といえるでしょう。
4. 普通株式(エクイティファイナンス)
(1)普通株式の概要
エクイティファイナンスは、投資家が、企業に資金を払い込み株主となるという資金調達の手法であり、企業が、デットファイナンスのように投資家に対して返済する必要がない点が特徴です。
株主は、他の金融機関、取引先、従業員といったステークホルダホルダーへの分配を終えた後で、残余価値がある場合に限り分配を得るという劣後的な地位に立たされます。
その反面、株主は債権者と異なり、原則として議決権を持ち、経営の方針に対して一定の介入をすることができます。
普通株式は、株式の中でも最も標準的な資金調達方法となります。
(2)普通株式のメリット
エクイティファイナンス一般に当てはまる最大のメリットは、融資のような返済義務がないため、成長過程のスタートアップ企業にとって財務的な負担が少ない点です。
投資家にとっても、企業価値が低い段階でスタートアップ企業に投資して、企業価値が増大した際のキャピタルゲイン(売却益)を得られるという点で、投資の強い動機付けになります。
また、後述する優先株式を発行せず、普通株式のみを発行していれば、株式の種類ごとに種類株主総会を開催する必要がないため、企業にとっては運用のコストを抑えることができます。
(3)普通株式のデメリット
普通株式のデメリットとしては、スタートアップ企業は将来の成長の見込みが不透明であるため、多額の資金調達が難しい点が挙げられます。
これは投資家にとって、スタートアップ企業へのエクイティファイナンスによる投資は、ハイリスクハイリターンであるため、シード段階での株式のエバリュエーションが低くなるためです。
▼デットファイナンスとエクイティファイナンスの比較
| デットファイナンス | エクイティファイナンス | |
| 出資者 | 債権者 | 株主 |
| 資金の返済義務 | あり | なし |
| 利息の返済義務 | あり | なし |
| 議決権に基づく経営への関与 | なし | あり |
| 企業価値が向上した場合の恩恵 | 受けられない | 受けられる |
| 投資家にとってのリスクリターン | ローリスクローリターン | ハイリスクハイリターン |
5. みなし優先株式(コンバーティブルエクイティの一種)
(1)みなし優先株式の概要
株式会社は、株主の権利の内容が異なる株式を発行することができます。
これを種類株式といいます。
種類株式のひとつに、優先的剰余金の配当を受けることができる優先株式というものがあります。
例えば、普通株式よりも20%大きい額の配当金を受けられる、普通株式への配当がない場合であっても優先株式に対しては1株当たり20円の配当金が支払いわれるといったものです。
さらに、株式の発行時には普通株式であるものの、次回の資金調達時に、優先株式に転換できることが合意された株式の形態もあり、これをみなし優先株式といいます。
(2)みなし優先株式のメリット
優先株式の発行にあたっては、優先株式の内容や契約の条項を検討する必要があります。
しかし、みなし優先株式の場合、発行時点では普通株式であるため、そのような検討のコストを先送りにすることができます。
優先株式発行に必要な手続は、事業本体に資金や人的コストを割きたいシード段階のスタートアップ企業にとっては相当の負担になるため、この負担を回避できる点がみなし優先株式のメリットになります。
(3)みなし優先株式のデメリット
みなし優先株式は発行時点では普通株式なので、すべての普通株主との間で優先株式への転換についての合意書を締結しなければなりません。
また、株主間の契約も必要となり、株主間契約交渉に時間を要することがあります。
株主が一定数以上の場合は、これらの点がネックになる可能性があることを踏まえてみなし優先株式の利用を検討する必要があります。
また、みなし優先株式は、発行時の出資金額が定額であるにもかかわらず、投資家に対して優先株主という価値の高い地位を付与することになる点も、資金調達を行う企業にとっては負担となります。
6. 有償新株予約権(コンバーティブルエクイティ)
(1)有償新株予約権の概要
有償新株予約権による資金調達は、次回の資金調達時に一定の金額を払い込むことで、投資家が株式の交付を受けることができるというものです。
投資家は、新株予約権の発行時ではなく、行使がされてはじめて株主となります。
(2)有償新株予約権のメリット
有償新株予約権は、発行時に企業価値について詳細のバリュエーションを行う必要がない点がメリットとなります。
また、新株予約権を発行しても、投資家がただちには株主となるわけではないため、シード期のスタートアップ企業にとっては株式数・株主数がいずれも限定され、株主総会の運営コストを軽減することができます。
さらに、後述する新株予約権付社債と比べて、償還義務がないことから、貸借対照表上の負債が膨らむことを回避でき、財務的な負担にもなりません。
(3)有償新株予約権のデメリット
起業促進による経済活性化のために、スタートアップ企業に投資する個人投資家に対しては税制優遇措置(エンジェル税制)が講じられています。
しかし、新株予約権については、エンジェル税制の対象外となるため、他の資金調達方法と比べると、投資家による投資の動機付けがひとつ減る点は新株予約権のデメリットになりえます。
また、新株予約権の発行時においては、株式の数が確定していません。
その後の権利行使のされ方次第では、経営株主を含めた既存株主の持ち分比率が低下し、株式が希釈化されるリスクが存在します。
したがって、既存株主と新たな株主との間の利益調整を適切に図る必要があります。
7. 転換社債型新株予約権付社債(コンパーティブルノート、コンバーティブルボンド)
(1)転換社債型新株予約権付社債の概要
転換社債型新株予約権付社債は、発行時には社債でありながら、発行後一定の条件下において、社債の元本を株式に転換できる特約が付されたものです。
(2)転換社債型新株予約権付社債のメリット
転換社債型新株予約権付社債の一つ目のメリットは、有償新株予約権と同様にバリュエーションを先延ばしにできる点です。
そして、投資家としては、当所発行された社債のまま資金を回収する方法と、社債を株式に転換することでリターンを得る方法とのいずれかを選択をすることができることが利点となります。
(3)転換社債型新株予約権付社債のデメリット
転換社債型新株予約権付社債は、発行時には社債としての性質を有するため、企業は返済義務を負います。
負債が膨らむという財務上の負担があり、特にスタートアップは財政的地盤が盤石ではないことが多く、その影響が大きくなります。
また、新株予約権と同様、転換社債型新株予約権付社債についても、株式に転換されなかった場合はエンジェル税制の対象とならないため、投資家にとっての恩恵が一つ減ります。
8. エクイティファイナンスの資金調達先~エンジェル投資家~
(1)エンジェル投資家とは・エンジェル投資家の目的
エクイティファイナンスによる出資を得る場合、エンジェル投資家、ベンチャーキャピタル、コーポレートベンチャーキャピタル、事業会社、プライベートエクイティファンド等複数の種類の投資家からの出資があり得ます。
これらのうち、シード期のスタートアップ企業としては、エンジェル投資から出資を受けることが一般的です。
このエンジェル投資家とは、起業して間もない企業に資金を出資する主に個人の投資家のことをいいます。
シード期のスタートアップ企業は、創業したばかりで知名度や実績があまりないことが多く、投資家にとっては不確定要素の大きいハイリスクな投資先と見られます。
エンジェル投資家は、このようなリスクを負いながらも、企業が成長した後に株式公開(IPO)やM&Aによる株式売却により多額のリターンを得たいと考えて、事業立ち上げ初期段階の将来性の高い企業に投資するのです。
(2)エンジェル投資家から投資を受けることのメリット
A)経営ノウハウや人脈の活用
エンジェル投資家は経営者として成功した人物であることが多く、広い人脈を持っています。
エンジェル投資家から投資を受けることで、優秀な人材や取引先などを紹介してもらうことで、事業成長を加速させることが期待できます。
また、エンジェル投資家から経営に役立つノウハウやアドバイスを得ることもでき、投資を受けるスタートアップ企業が起業や経営の経験を持っていなかったとしても、それを補うという効果もあります。
B)投資判断の早さ
エンジェル投資家は、主にアーリー期以降の投資家となるベンチャーキャピタルと比べて投資判断がスピーディーであるという特徴を持ちます。
ベンチャーキャピタルは、企業に投資するという決定を行うにあたって、事業の成長性・将来性、法令・会計基準の順守、訴訟リスク等についてのデューデリジェンスに相当程度の時間を費やすのが通常です。
これは、ベンチャーキャピタルがファンドへの出資者に対して説明責任を負うためです。
これに対してエンジェル投資家は、ある程度の精査は行うものの、投資判断を厳格に行う必要が高いベンチャーキャピタルと比べて投資決定の判断が比較的早い点が、投資を受けるスタートアップ企業にとってのメリットとなります。
(3)エンジェル投資家から投資を受けることのデメリット
A)投資契約書の締結
上述のとおり、シード期のスタートアップ企業への投資は高いリスクがつきものです。
したがって、エンジェル投資家としては、このようなリスクを回避するために投資家に有利な特約を盛り込んだ投資契約書の締結を求めるケースが多くあります。
エンジェル投資家が提案する投資契約書をそのまま受け入れて署名してしまった場合は、出資後にエンジェル投資家の経営に対する関与が強まる、企業が上場できなかった場合に高額での株式の買収を求められるといった事態になることがありえます。
したがって、エンジェル投資家から投資を受ける場合は、出資金額や出資方法が決まればよいというものではなく、投資契約書に含まれるリスクを法的な知見からレビューし、場合によってはエンジェル投資家と交渉するという慎重な対応が必要となります
B)ベンチャーキャピタルと異なるリスク
ベンチャーキャピタルは、法人または法人が運営するファンドであるため、金融庁の監督のもと、投資家としての適格が法的に担保されています。
これに対して、エンジェル投資家は、法的な担保はなく、投資家の属性がどのようなものであるかを知る術は限定されています。
したがって、エンジェル投資家と名乗る者が反社会的勢力だった場合、出資後に法外な要求を突き付けられる、IPOができなくなる、優秀な人材が確保できなくなる、他の投資家からの出資が得られなくなるといったリスクがありえます。
事業の収益性が高いにもかかわらず、企業の成長が阻まれるのはなんとしても避けるべき事態です。
このような理由から、エンジェル投資家の選定には慎重を要すると言えます。
(4)エンジェル投資家とマッチングする方法
エンジェル投資家とマッチングする方法としては、知人から紹介を受ける、ビジネスコンテストで投資家に対して事業のプレゼンテーションを行う、マッチングサイトやSNSを利用するといったものが挙げられます。
もっとも、そもそもの人脈がない、イベント参加やサービス利用に費用その他の条件があるといった場合には、そもそもエンジェル投資家とマッチすることができないこともありえます。
そして何よりも上述した反社会的勢力のケースも含め、エンジェル投資家の質が確保されていない点もリスク要因です。
したがって、スタートアップ企業としては、信頼できるルートでエンジェル投資家とのつながりを得ることが重要となってきます。
9. シード期の資金調達上の課題と法律専門家の役割
(1)シード期の資金調達上の課題
上記のとおり、シード期のベンチャー企業にとって、選択しうる資金調達方法は様々です。
それぞれにメリットとデメリットがあり、スタートアップ企業が置かれている状況は個々に異なるため、当該企業にとって最も適切な方法を選択することが、スタートアップ企業の資金調達ひいてはその後の事業のためには不可欠となります。
また、投資家と企業との間の条件調整や、さらに投資家が多数となったり、複数の資金調達を組み合わせたりする場合は、投資家間での利益調整も重要となってきます。
具体的には、株式の発行条件、優先株式の内容、新株予約権の発行条件、投資契約等の条項をち密に検討する必要性があります。
(2)法律専門家の役割
XP法律事務所は、スタートアップ法務・資金調達法務の豊富な経験を有しており、個々のベンチャー企業の実情にあったスキーム提案が可能であると当時に、多数の企業間交渉経験を有しており、エンジェル投資家との交渉にあたっても強力なエージェントとなります。
また、スタートアップ企業の資金調達に際して必要な投資家との交渉、投資契約書リスクの正確なレビュー、定款変更登記等の複雑な工程をワンストップで対応するサービスを提供している点もXP法律事務所の特徴です。
さらに、法律事務所とベンチャーキャピタルが連携するという最先端の取り組みを行っており、企業のIPOやM&AによるEXITを見据えた投資家とのマッチングをサポートいたします。
