薬機法(旧薬事法)
【2024年最新】薬機法・景品表示法・医師法からみるエステサロンの広告規制について徹底解説
エステティック業に携わる方にとって、サロンの長所を強調し、法律を遵守した効果的な広告を行えるかが大きな課題ではないでしょうか。専門知識を要する広告の訴求表現はもちろん、各法律を遵守するためにも、薬機法や景品表示法、医師法などの概要や違反した際のリスクなど、エステサロンを取り巻く広告規制について解説させていただきます。
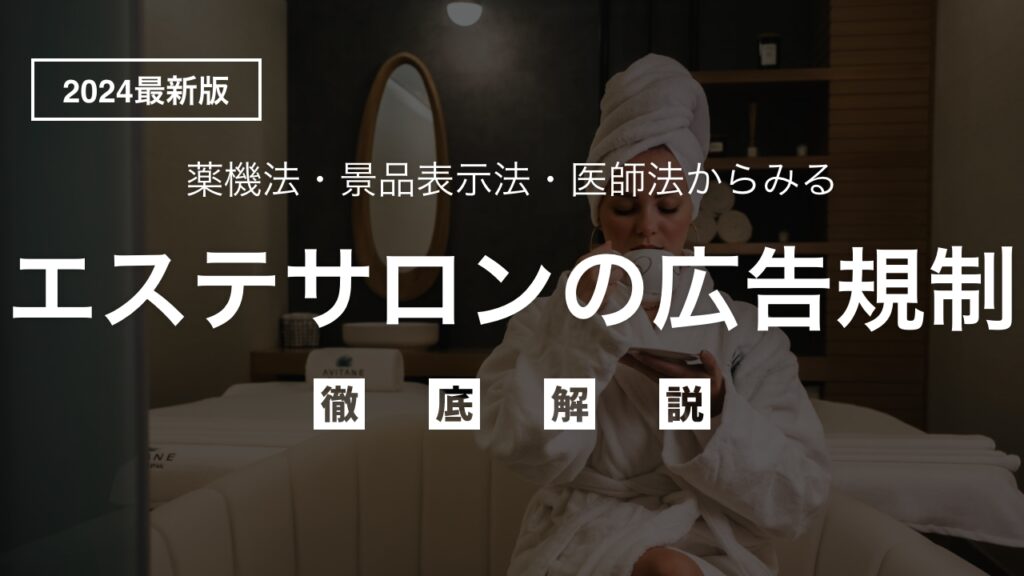
arrow_drop_down 目次
エステティック業に携わる方にとって、最も効果的な集客方法に「広告」と答える方も少なくないのではないでしょうか。
エステサロンをはじめとする美容分野は、広告規制を筆頭に、法的制約の多い業界でもあります。
そのため、広告規制に係る法律を遵守し、当該エステサロンの長所を強調しつつ、いかに効果的な広告を行い、集客に繋げるかが、大きな課題ではないでしょうか。
広告の訴求表現は専門知識を要する他、法律ごとに細かく規定されており、「知らず知らずのうちに法律に違反していた」などの状況も想定されます。
各法律を遵守するためにも、エステサロンの広告に関連する法律と規制事項について学ぶことは、サロン経営するにあたって重要なポイントとなるのです。
本記事では、薬機法をはじめ、広告規制に係る「景品表示法」や「医師法」などの関連法令の概要や注意事項、法令に違反した際の罰則など、皆さまの疑問を解決するため、エステサロンを取り巻く広告規制について解説させていただきます。
XP法律事務所では、エステをはじめとする美容業界に携わる方へ向け、広告に関するリーガルチェックや訴求表現のアドバイスをはじめ、”新しい時代の法律事務所を創造する”という使命を掲げ、ビジネス全般に渡り、クライアント単位でトータルソリューションを提供しています。
特に、美容分野の広告表現規制に関連する法令は、「薬機法」とこの法令に係る「化粧品等の適正広告ガイドライン」や「医薬品等適正広告基準」をはじめ、「景品表示法」や「医師法」など、経営に関する部分まで、網羅的に判断する必要があります。
法的な課題に対し、ビジネスのリーガルコンサルタントとして、相談者様のニーズを汲み取り、最適な解決へ向け、サポートいたします。
美容分野の広告に関する助言や審査、薬機法をはじめとする法令についてご不明点がある場合には、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。
エステサロンの広告を行うにあたって重要な法律

こちらの章では、エステサロンの広告を作成するにあたって注意すべき法律についてご紹介します。
結論として、気をつけるべき法律は、次の通りです。
- 薬機法
- 景品表示法
- 特定商取引法
特に、エステサロンを経営される方やサロンの集客担当者、広告作成を依頼された代理店、ライターの方は、上記の法律について、正しく理解する必要があることに留意しましょう。
それでは、各法律について解説していきます。
「薬機法(やっきほう)」とは

エステサロンの広告表現と規制についてご紹介するにあたり、まず「薬機法」についてご紹介します。
エステサロンで化粧品などを販売する場合に加え、サロン内で使用・販売する器具が医療機器に該当する際に、覚えておくべき法律の一つです。
そもそも、「薬機法(旧:薬事法)」とは、正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」を略した名称を指します。
薬機法は、「製品の安全性と品質を確保し、保健衛生の向上を図ること」を目的としており、薬機法の対象となる製品の製造や販売をはじめ、流通や表示、広告に関する規律を行う法律を指します。
第1条:目的
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
薬機法の規制対象となる分野は、次の通りです。
また、上記の製品を総称し、「医薬品等」と呼びます。
薬機法についての詳細については、こちらの記事をご覧ください。
エステサロンが注意すべき薬機法の「広告規制」とは

こちらの章では、「薬機法」において、エステサロンが注意すべき規制事項である「広告規制」についてご紹介します。
前提として、薬機法の違反行為は、次の通りです。
- 無許可営業・無登録営業
- 医薬品等の取り扱いに関する違反
- 広告規制違反★
上記の中でも、エステサロンに適用される規制事項は、《3. 広告規制違反》となります。
薬機法の「広告規制違反」とは

薬機法では、薬機法の対象分野の製品について広告を行う際に、次の行為について規制が定められています。
- 虚偽・誇大広告等の禁止(第66条)★
- 特定疾病用医薬品等の広告の制限(第67条)
- 承認前医薬品等の広告の禁止(第68条)★
薬機法における広告の定義と該当媒体・該当者について
前提として、薬機法における「広告」とは、次の3要件の通りです。
薬機法で、広告と見なされるカテゴリーは、「一般消費者向けのすべての広告媒体」を指します。
具体的には、広告を掲載した媒体そのものを指します。
テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、Webサイト、アフェリエイト広告、SNS広告(Instagram・TikTokなど)、チラシ・ポスター・パンフレット、DM(ダイレクトメール)、ブログ、電子メールなど
広告規制の対象者は幅広く、エステサロンの広告作成に携わった「すべての人」となっており、広告主(依頼者)をはじめ、法人・個人、フリーランスであるか問われないことをご留意ください。
| 広告規制の対象者 | |
| 広告主・広告代理店 | メディア運営事業者 |
| レビューサイト運営事業者 | ライター |
| アフェリエイター | インフルエンサー |
広告規制の概要についてご紹介したところで、エステサロンの広告を作成する場合に深く関わってくる「虚偽・誇大広告等の禁止」と「承認前医薬品等の広告の禁止」について、解説していきます。
虚偽・誇大広告の禁止(第66条)
薬機法における広告規制で禁止されている行為の一つに「虚偽・誇大広告」が挙げられます。
具体的には、医薬品等の《名称・製造方法・効能・効果・性能》に関して、虚偽または誇大な記事や広告を広めることを禁止しています。
エステサロンの場合、『サロン内で販売する化粧品等』や『医療機器に該当するサロン内で使用・販売する器具』が対象です。
重ねて、医薬品等の効果・効能・性能に対して、次の行為も規制されていることにご留意ください。
- 医師などが保証したと誤解されるおそれのある広告
- 堕胎を暗示するものやわいせつな文書・図画を用いること
特に、化粧品等の効果・効能の範囲については、「化粧品の効能の範囲の改正について」で定められており、この範囲内で表現を行う必要があるため、ご注意ください。
第66条:誇大広告等
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。
3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。
承認前医薬品等の広告の禁止(第68条)
続いて、「未承認医薬品等」に係る禁止事項についてご紹介します。
こちらの規制で禁止されているのは、承認前の医薬品等の《名称・製造方法・効能・効果・性能》について、広告する行為です。
併せて、医薬品等に該当しない製品にも関わらず、医薬品等と誤認させるような効能・効果の表示・広告(薬でないもの」を「薬」のように宣伝すること)も「未承認の医薬品等」であると判断されます。
具体的には、「医療機器に該当するサロン内で使用・販売する器具」について、承認がないにも関わらず広告を行うことは、薬機法違反の該当行為です。
特に、医療機器の使用や販売、広告を行う場合には、薬機法以外の法律にも接触する可能性があります。
エステサロンで器具を使用・販売する際には、該当器具が該当する分野をしっかりと把握し、正しい表示を行うことが重要です。
第68条:承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止
何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。
「薬機法」に違反した場合の罰則

先にご紹介した「広告規制」をはじめ、薬機法に違反した場合には、次の処遇を受ける可能性があります。
- 行政処分
- 課徴金納付命令
- 刑事罰
各項目の概要については、次の表をご覧ください。
| 項目 | 具体的な内容 |
| 1. 行政指導 | 【行政指導は段階的に行われ、命令に従わない場合には、課徴金納付命令が下される】 《行政処分までの流れ》 1. 行政処分 2. 業務改善命令 3. 措置命令 4. 業務停止命令 5. 許可・登録の取消 6. 課徴金納付命令★ |
| 2. 課徴金納付命令 | 【第66条「虚偽・誇大広告等の禁止」に違反した場合】 ■ 支払い金額: 虚偽・誇大広告を行っていた期間中に得られた売上金額の4.5% ■ 支払い期間: 違反行為の開始日から数えて、最長で3年間 |
| 3. 刑事罰 | 【 第84条「無許可製造・販売」に違反した場合】 ■ 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方 【第85条「虚偽・誇大広告」に違反した場合】 ■ 2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方 【第86条「特定疾病用の医薬品等に関する広告」に違反した場合】 ■ 1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方 |
各違反行為の詳細については、こちらの記事をご参考にしてください。
従って、薬機法について正しい知識を学び、一人ひとりが法律を遵守するよう努めることが重要です。
薬機法における「医療機器」と「美容機器」との違いとは
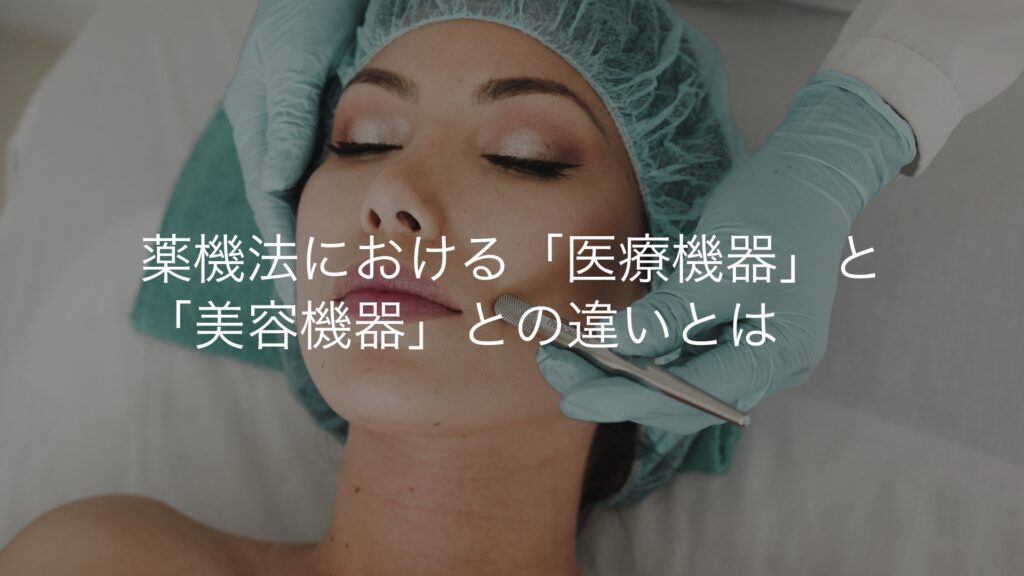
先ほど、医療機器の使用や販売、広告を行う場合には、薬機法以外の法律にも接触する可能性がある、とご紹介しました。
前提として、薬機法における「医療機器」とは、次のように定義されています。
第2条第4項:医療機器の定義
この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
一方、法律上「美容機器」について定義されるものはありません。
従って、人や動物の診断・治療・予防に使用される医療機器に該当しないものと言えるでしょう。
美容機器を医療機器ではないにも関わらず、医療機器のように標榜すること
薬機法の違反行為の一つである広告規制の「承認前医薬品等の広告の禁止(第68条)」の通り、美容機器にも関わらず、医療機器のような効果・効能を表示した場合には、薬機法に接触する可能性があります。
具体的には、実際の効果・効能を問わず、「医療機器にあたる」と見なされ、薬機法違反として先にご紹介した罰則が課せられてしまうのです。
また、当該器具の承認がないにも関わらず、販売等を行った場合も同等の扱いです。
さらに、広告や表示内容により、「虚偽・誇大広告の禁止(第66条)」にも違反している可能性があります。
しっかりと広告や表示内容を精査し、薬機法を遵守するよう努めることが重要です。
法律違反と判断されるのは、薬機法だけではなく、次の法律にまでその範囲が及ぶ可能性があるため、注意しましょう。
| 法律名称 | 法律違反と見なされる行為 |
| 景品表示法 | ■ 不当表示「優良誤認表示」 【具体例】実際には医療機器の効果・効能を持ち合わせていないにも関わらず、あたかも医療機器のような効果・効能を表示する行為 |
| 医師法(第17条) | ■ 第17条「医師でなければ、医業をなしてはならない。」 【具体例】エステサロンで使用する器具が医療器具に該当する場合、その器具を用いて施術を行うこと |
併せて押さえておきたい「医師法」とは

エステサロンの広告を行う上で関連してくる「医師法」についても解説させていただきます。
「医師法」とは、医師の免許をはじめ、国家試験の制度、臨床試験、医療業務などを規定した法律です。
この法律の違反行為として、医業に関連する事項として、次の項目を禁止しています。
- 医師以外の者が医業をすること
- 虚偽または不正の事実に基づいて医師免許を受けること
- 医師以外の者が医業を行い、医師の名称や紛らわしい名称を用いること
- 医業の停止を命じられたのにも関わらず、医業を行うこと
- 医師が診察をしないで治療すること
特に押さえておきたいのは、先にも少し触れましたが、次の項目です。
医師法17条に違反した場合、「3年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはこれを併科する」といった罰則を受けることになります。
従って、エステサロンでの医療行為並びに施術者、つまりエステティシャンは、医師ではないため、医療行為は行えません。
医療行為が禁止されているにも関わらず、施術内容について、「〇〇(病名)予防に効果がる」など、医療行為であると誤認を与えるような表現を行った場合、景品表示法の不当行為の一つである「優良誤認表示」に接触する可能性が高いです。
万が一違反した場合には、景品表示法違反として、罰則が適用されるため、ご注意ください。
第1条・1条の2:総則
第一条 医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
第一条の二 国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(以下単に「大学」という。)、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
エステサロンが確認すべき「景品表示法」における広告表現規制

エステサロンの広告を行う上で重要な法律として、続いてご紹介するのは、「景品表示法(けいひんひょうじほう)」です。
「景品表示法」とは、正式名称「不当景品類及び不当表示防止法」を略した名称で、商品や役務(サービス)の取引を行うにあたって、不当な景品類や表示による消費者の誘引を防止するための法律を指します。
第1条:目的
この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とする。
ちなみに、「景品」とは、次に提示する意味が含まれています。
- 顧客を誘引するための⼿段
- 事業者が供給する商品または役務(サービス)の取引(不動産に関する取引を含む)に付随して相手方に提供する物品
- 金銭、その他の経済上の利益で、内閣総理大臣が指定するもの
《3. 内閣総理大臣が指定するもの》とは、次の項目を指します。
- 物品・⼟地・建物・その他の⼯作物
- ⾦銭・⾦券・預⾦証書・当せん⾦付証票及び公社債・株券・商品券その他の有価証券
- きょう応(映画・演劇・スポーツ・旅⾏・その他の催物等への招待または優待を含む)
- 便益・労務・その他の役務
※正常な商慣習(商取引の過程において形成された慣習)にあたって、値引またはアフターサービスと認められる経済上の利益及び正常な商慣習やその取引に係る商品または役務に付属すると認められる経済上の利益は含まれない
また、景品表示法の対象である「顧客を誘引する手段として用いられる様々な表示」として次の媒体が挙げられます。
テレビ、新聞、雑誌、ラジオ、Webサイト、インターネット広告、セールストーク、訪問販売、電話、店内広告、パッケージ、チラシ・ポスター・パンフレットなど
薬機法とは異なり、企業から広告・宣伝の依頼を受けたインフルエンサー等の第三者は規制の対象外です。
エステサロンが注意すべき「優良誤認表示」と「有利誤認表示」とは

前提として、景品表示法において、「不当表示」を行うことを禁止しています。
「不当表示」であると見なされる規制事項は、次の通りです。
- 優良誤認表示★
- 不実証広告規制
- 有利誤認表示★
- 商品または役務の取引に関する事項について、一般消費者に誤認されるおそれがある表示出会って、内閣総理大臣が指定する表示
上記の中でも、エステサロンの広告を行うにあたって適用される規制事項は、《1. 優良誤認表示》《3. 有利誤認表示》となります。
それでは、各規制事項について、解説していきます。
優良誤認表示(第5条1項)
まずご紹介するのは、「優良誤認表示」についてです。
具体的には、一般消費者に対し、事業者が自己の提供する商品やサービスの【品質・規格・その他の内容】について、顧客を誘引する手段として用いられる様々な表示において標ぼうすることを禁止しています。
- 実際の商品やサービスよりも著しく優良であると表示すること
- 事実に相違して、競合事業者よりも著しく優良であると表示すること
エステサロンにおいて、取り扱う商品やサービスの価格といった取引条件について広告する際には、上記に違反しないよう徹底しましょう。
重ねて、優良誤認違反に該当する表示の一例として、次の表現を禁止しています。
特に、エステサロンの施術に関しては、事実に基づく根拠や数値を示すことが困難であることから、訴求表現には慎重になることが重要です。
万が一、一般消費者に対し、優良誤認を与えた場合、故意・過失問わず、景品表示法に接触したことになります。
すべての商品やサービスが規制の対象となっているため、合理的な根拠のない効果・効能を表示することは、ご注意ください。
第5条1項:不当な表示の禁止
一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
有利誤認表示(第5条1項)
続いてご紹介するのは、「有利誤認表示」です。
具体的には、商品やサービスの【価格、取引条件(数量・アフターサービス・保証期間・支払い条件)】について、次のように表示することを禁止しています。
- 商品やサービス取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認される表示
- 商品やサービス取引条件について、競合事業者に比べ、著しく有利であると消費者に誤認される表示
エステサロンで取り扱う商品やサービスの価格といった取引条件について広告する場合には、表現について慎重になる必要があります。
具体例として、商材を問わず、商品やサービスの販売価格を記載する際に、自社の販売価格(提供価格)よりも、価格の高いものを併記する行為を二重価格表示と呼びます。
特に、比較対象とする価格内容について、適正な表示が行われていない場合には、有利誤認表示と見なされてしまう可能性があるため、ご注意ください。
有利誤認表示違反に該当する表示の一例として、次の表現を禁止しています。
第5条2項:不当な表示の禁止
二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
「景品表示法」に違反した場合の罰則

景品表示法の違反行為である「不当表示」を行った場合、次の処遇を受ける可能性があります。
- 措置命令
- 課徴金納付命令
- 適格消費者団体による差止請求
- 懲役刑
各項目の概要については、次の表をご覧ください。
| 項目 | 具体的な内容 |
| 1. 措置命令 | 【違反行為が認められた場合】 調査や弁明の機会が与えられ、必要に応じた措置命令」を行います。 《措置命令の流れ》 1. 【公正取引委員会・消費者庁・都道府県】による外部からの情報提供及び職権探知 2. 上記機関による調査 3. 弁明の機会・証拠の提出 4. 措置命令 5. 課徴金納付命令 |
| 2. 課徴金納付命令 | 【「第5条1項:優良誤認表示」「第5条2項:有利誤認表示」に違反した場合】 ■ 支払い金額:不当表示違反の期間中に得られた売上額に3%を乗じた金額 ■ 支払い期間:3年間の上限 |
| 3. 適格消費者団体による差止請求 | 【「第5条1項:優良誤認表示」「第5条2項:有利誤認表示」に違反した場合】 ■「適格消費者団体*」が事業者に対し、上記の違反行為に該当する広告表示の停止を書面で求めることができる ■ 事業者が応じない場合、広告表示の停止を求める訴訟を起こすことも可能 |
| 4. 懲役刑 | 【措置命令を受けても従わず、虚偽の報告や違法な広告表示を継続した場合】 ■ 2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方 |
不不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止請求権を適切に行使できる専門性などの要件を満たしたうえで、内閣総理大臣によって認定された消費者団体のこと
エステサロンの広告表現に関するご相談はXP法律事務所へ

ここまで、薬機法における化粧品の前提知識をはじめ、薬機法における化粧品広告の概要や注意事項、薬機法や景品違反した際のリスクや罰則など、エステサロンの広告表現を取り巻く規制について解説をしてきました。
薬機法に違反した場合には、行政処分・課徴金納付命令・刑事罰の対象に。
景品表示法に違反した場合には、措置命令・課徴金納付命令・適格消費者団体による差止請求・懲役刑の対象となる可能性があります。
特に、薬機法に係る広告規制に関しては、広告主や法人・個人か、フリーランスであるか否かを問わず、広告にに携わった全ての人が(薬機法の)“対象者の1人”と見なされるため、一人ひとりが法律を遵守するよう努めることが大切です。
XP法律事務所では、エステをはじめとする美容業界に携わる方へ向け、広告に関するリーガルチェックや訴求表現のアドバイスをはじめ、”新しい時代の法律事務所を創造する”という使命を掲げ、ビジネス全般に渡り、クライアント単位でトータルソリューションを提供しています。
薬機法等のリーガルチェックはもちろん、広告における訴求表現を行うことは、専門性が高く、どれだけ確認をしても、不安が残ってしまう方も少なくないのではないでしょうか。
弁護士をはじめとする法律の専門家に依頼することで、不正確な情報の発信やトラブルを未然に防げるだけでなく、サービスを利用する消費者の安全性を守ることにも繋がります。
法的な課題に対し、ビジネスのリーガルコンサルタントとして、相談者様のニーズを汲み取り、最適な解決へ向け、サポートいたします。
美容分野の広告に関する助言や審査、薬機法をはじめとする法令についてご不明点がある場合には、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
【XP法律事務所】
- 代表弁護士:今井 健仁(第二東京弁護士会)
- 所在地:〒104-0061 中央区銀座1-15-4 銀座一丁目ビル13階
- TEL:03-6274-6709(銀座本店)
- FAX:03-6274-6710(銀座本店)
- ホームページ:https://xp-law.com/
