薬機法(旧薬事法)
【2023年最新】薬機法における(旧薬事法)における再生医療等製品と違反リスクを徹底解説!
再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の広告を行う際には、広告に携わる人すべての人が規制の対象者となり、法律に接触してしまう可能性があります。本記事では、再生医療等製品の概要に加え、再生医療等製品広告における注意事項や罰則など、薬機法における再生医療等製品を取り巻く広告規制について、徹底解説させていただきます。
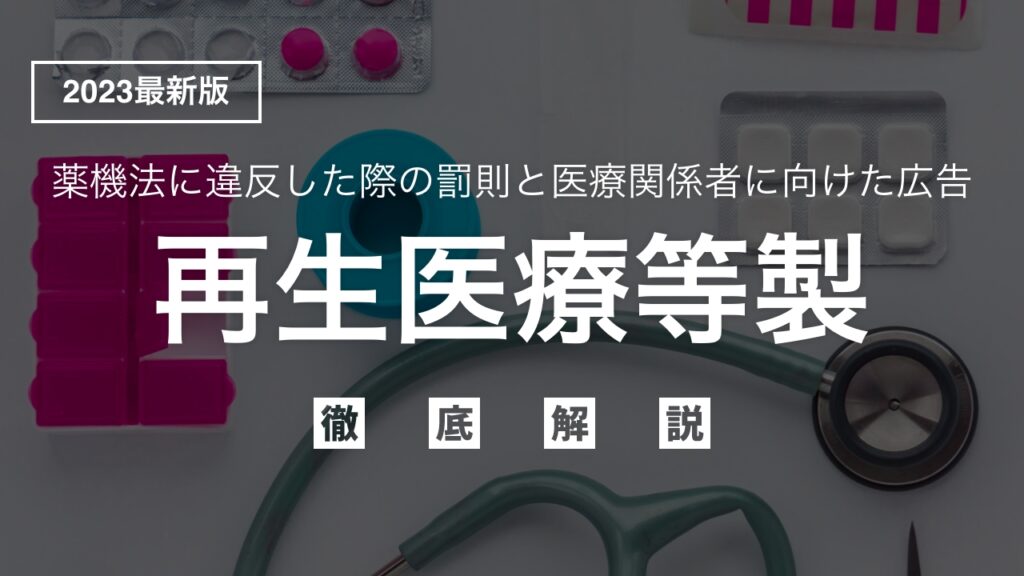
arrow_drop_down 目次
皆さんは、再生医療等製品とは何かご存知でしょうか?
再生医療等製品とは、「人または動物の生きた細胞や組織を培養等の加工を施し作成されたもので、体の構造・機能の再建・修復・形成や疾病の治療・予防、遺伝子治療を目的として使用されるもの」を指します。
具体的には、昨今話題にもなった山中伸弥氏の教授が樹立し、ノーベル章を受賞したiPS細胞もこの再生医療等製品の一つに該当するのです。
ただし、再生医療等製品の広告を行うことは、医師または歯科医師の指導がなければ危害が生ずるおそれがあるため、厚生労働省令で指定された再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限しているためご注意ください。
違反しようという意図がない場合でも、薬機法に接触することで、行政処分や課徴金、刑罰の対象となるため、製品の取り扱いには慎重になることが大切です。
従って、医薬品の製薬会社や製造者など、その医薬品を取り扱う企業の担当者の方は、薬機法を正しく理解し、薬機法を遵守するよう徹底することが重要です。
薬機法の概要をはじめ、薬機法における再生医療等製品の概要や注意事項、薬機法に違反した際のリスクや罰則など、皆さまの疑問を解決するため、徹底解説させていただきます。
XP法律事務所では、薬機法に関するリーガルチェックや広告の訴求表現のアドバイスをはじめ、”新しい時代の法律事務所を創造する”という使命を掲げ、ビジネス全般に渡り、クライアント単位でトータルソリューションを提供しています。
薬機法に係る分野の広告に関する助言や審査、ご不明点がある場合には、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。
そもそも薬機法とは

再生医療等製品を解説するにあたって、薬機法の概要や定義からご紹介させていただきます。
まず、「薬機法(やっきほう)」とは、正式名称「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」のことで、現在の法令名を略した名称のことです。
以前は「薬事法(やくじほう)」と呼ばれていましたが、2014年11月25日に施行された「薬事法等の一部を改正する法律」により、現在の名称に変更されました。
薬機法の目的は、次のように定義されており、薬機法の対象となる製品の製造や販売をはじめ、流通や表示、広告に関する規律を行っています。
第1条:目的
この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。
薬機法の規制対象は、次の5分野となり、これらの製品を総称し「医薬品等」と呼びます。
薬機法に違反した場合【行政処分・課徴金納付命令・刑事罰】などの処遇を受ける可能性があるため、ご注意ください。
従って、薬機法について正しい知識を学び、一人ひとりが法律を遵守するよう努めることが重要です。
薬機法における「再生医療等製品」とは
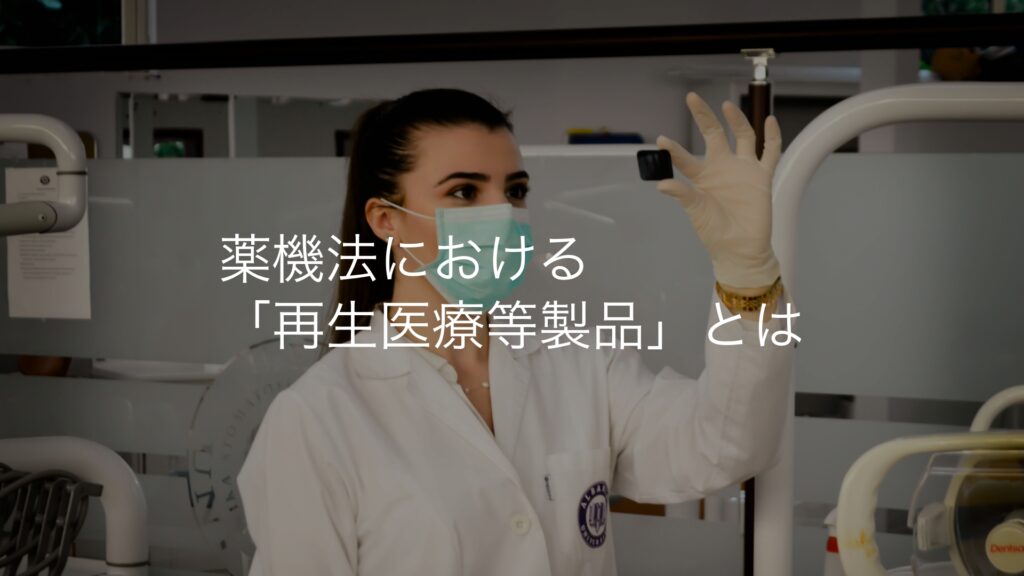
こちらの章では、薬機法における「再生医療等製品」についてご紹介いたします。
特に、再生医療等製品は 、人の細胞等を用いるため、品質が均一ではないことに加え、有効性の予測が難しいケースもあるという点が特徴です。
第2条第9項:薬機法の定義
この法律で「再生医療等製品」とは、次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。
1. 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したもの
イ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成
ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防
2. 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの
再生医療等製品の分類

再生医療等製品は次の3つの項目に分類されます。
- 第一種再生医療等
- 第二種再生医療等
- 第三種再生医療等
再生医療等製品の詳細は次の図の図をご覧ください。
| 分類 | 内容 |
| 第一種再生医療等 | 【安全性へのリスクが高いもの】 ■ 提供に係る手続・第一種再生医療を行う場合、「特定認定再生医療等委員会」に「治療の提供計画」を提出し、厚生労働大臣の承認を受ける必要がある (例「ES細胞」「iPS細胞」「他人の幹細胞を利用するもの」など) |
| 第二種再生医療等 | 【安全性へのリスクが中程度のもの】 ■ 提供に係る手続・第二種再生医療を行う場合、「特定認定再生医療等委員会」の意見を聞き、「治療計画」を厚生労働大臣に提出する必要がある (例「患者自身の体性幹細胞などを利用するもの」など) |
| 第三種再生医療等 | 【安全性へのリスクが低いもの】 ■ 提供に係る手続・第三種再生医療を実施する場合、「認定再生医療等委員会」の意見を聞き、「治療計画」を厚生労働大臣に提出する必要がある (例「加工を施した体性細胞を利用したもの」など) |
なお、「提供に係る手続」とは、次の項目を行おうとする機関へ向けたもので、事前に手続をするよう義務付けられています。
- 再生医療等を提供しようとする医療機関
- 再生医療等で使用する特定細胞加工物を製造する場合
万が一、規定の手続をせず、上記を遂行した場合には、法律違反として、罰則が適応されるため、ご注意ください。
再生医療等実施の流れ

先にご紹介した、再生医療等実施の流れは次の通りです。
| 再生医療等実施の流れ | 具体的な内容 |
| 1. 再生医療等提供計画の作成 | ◼️特定認定再生医療等審査委員会への申請 ◎ 申請の際はさまざまな書類を要する |
| 2.「認定再生医療等委員会」または「特定認定再生医療等委員会」にて助言・審査 | ■ 第三種再生医療等:認定再生医療等委員会 ■ 第一種・第二種再生医療等:特定認定再生医療等委員会 ※「認定再生医療等委員会」:再生医療等技術や法律の専門家等の有識者からなる合議制の委員会で、一定の手続により厚生労働大臣の認定を受けたもの ※「特定認定再生医療等委員会」:認定再生医療等委員会のうち、特に高度な審査能力、第三者性を有するもの |
| 3. 厚生労働省へ再生医療等提供計画の提出・承認 | ■ 提出後、第二種・第三種再生医療等の場合は、提供開始する ※提供計画を厚生労働省に提出せず、再生医療等を提供した場合は罰則が課される |
| 4. 厚生科学審議会での審査・助言 | ■ 第一種再生医療等の場合、厚生科学審議会に通される。 その結果を踏まえ、再生医療等提供計画の変更命令が出された際には、90日間の提供制限期間が設けられる。 |
| 5. 提供開始 | 提供開始時には、厚生労働省の許可を取得した |
薬機法における「広告」について

結論から申し上げると、再生医療等製品の広告を行うことは、医師または歯科医師の指導がなければ危害が生ずるおそれがあるため、厚生労働省令で指定された再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限しているためご注意ください。
薬機法において、この「広告規制」に違反した場合、懲役刑や罰金などの厳しい罰則が適用されることになります。
前提として、薬機法における「広告」とは、次の通りです。
重ねて、薬機法において「広告」とは、次のようなカテゴリーを指し、一般消費者向けの広告媒体すべてが該当します。
| 広告の具体例 | |||
| テレビ | 新聞 | 雑誌 | ラジオ |
| Webサイト | アフェリエイト広告 | SNS広告 | チラシ・ポスター・パンフレット |
| ダイレクトメール(DM) | ブログ | 電子メール | – |
薬機法の対象者は、広告主や法人・個人か、フリーランスであるか否かを問わず、広告に関係する、すべての人が対象です。
重ねて、インフルエンサーの利用傾向の高い、InstagramのストーリーやTikTokの動画などに関しても、薬機法の対象となるためご注意ください。
万が一、薬機法に違反した場合、繰り返しとなりますが、厳しい罰則が適用されることになります。
また、薬機法に違反する前に、法律の専門家である弁護士に相談するなど、遵守状況をはじめとする具体的なアドバイスを仰ぐことで、法律遵守に繋がるのではないでしょうか。
薬機法違反にあたる行為の例

冒頭、薬機法に違反した場合、懲役刑や罰金などの厳しい罰則が適用される可能性があると、ご紹介しました。
こちらの章では、薬機法における具体的な違反行為について、解説いたします。
薬機法における違反行為は、次の3点です。
- 無許可営業・無登録営業
- 医薬品等の取り扱いに関する違反
- 広告規制違反
上記の違反行為を簡単にまとめると次の図の通りです。
| 違反行為 | 具体的な内容 |
| 1. 無許可営業・無登録営業 | ■ 許可・登録の義務:医薬品等の製造・販売などの事業を行う場合、許可・登録が必要 【第49条1項】 |
| 2. 医薬品等の取扱いに関する違反 | ■ 処方箋の販売:医師・歯科医師・獣医師から処方箋の交付を受けていない者に対する販売の禁止【第49条1項】 ■ 医薬品の表示・記載・直接の容器等の記載事項【第50条・51条】:直接の容器または直接の被包に規定事項の記載を必須とする ■ 容器等への符号(バーコード)等の記載【第52条1項】:容器又は被包に電子情報処理組織を使用する方法やその他の情報通信の技術を入手するために必要な番号や記号、その他の符号の記載必須とする ■ 添付文書等の記載事項【第52条2項】:要指導医薬品、一般用医薬品その他の厚生労働省令で定める医薬品は、直接の容器や直接の被包、添付文書などに規定事項の記載を必須とする ■ 記載事項の記載方法【第53条】:記する際は、他の文字や記事、図画または図案に比較し、一般消費者にとって見やすい場所にされていなければならない |
| 3. 広告規制違反 | ■ 虚偽・誇大広告等の禁止【第66条】 ■ 特定疾病用医薬品等の広告の制限【第67条】 ■ 承認前医薬品等の広告の禁止【第68条】 |
各違反行為の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
再生医療等製品の広告をするにあたって

先ほど、薬機法の違反行為の一つとして広告規制が設けられているとご紹介しました。
繰り返しとなりますが、医療関係者以外の一般消費者に向けた、再生医療等製品の広告を行うことは薬機法で禁止されています。
本章では、医療関係者に向けた広告であると仮定し、厚生労働省の「医薬品等適正広告基準」をもとに、留意しなくてはならない規制と具体例についてご紹介します。
1. 製造方法関係の表現

医薬品等適正広告基準では、「製造方法関係についての表現」について、次のように規制しています。
2 製造方法関係
医薬品等の製造方法について実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性 について事実に反する認識を得させるおそれのある表現をしてはならない。
具体的には、次のように定めています。
1. 製造方法の優秀性についての表現
次のような表現を行うことを禁止しています。
| 禁止項目 | 具体例 |
| 1. 最大級の表現 | 「最高の技術」「最先端の製造方法」 |
| 2. 最大級の表に類する表現 | 「近代科学の粋を集めた製造方法」「理想的な製造方法」「家伝の秘法により作られた」 |
ただし、「製造部門」「品質管理部門」「研究部門」などを広告の題材として扱う場合、次の条件を満たしている場合には、表現が可能となります。
- 事実に基づいた表現
- 製造方法等の優秀性に加え、他社・他製品との比較において誤認を与えない表現
2. 特許について
特許に関する虚偽または誇大な広告を行った場合、薬機法に接触するため、注意しましょう。
ただし、特許を取得した点が事実である場合、後ほどご紹介する第4の10「医薬関係者等の推せん」の規約に従うよう義務付けられています。
3. 研究について
製造販売業者等がその製品にかかわる研究内容を述べる場合、事実を正確かつ強調せずに表現するよう努めましょう。
2. 承認等を要する医薬品等の効果効能等の表現の範囲

医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「承認等を要する医薬品等の効果効能等の表現の範囲」について、次のように規制しています。
(1)承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲
承認等を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」という。) についての表現は、明示的又は暗示的であるか否かにかかわらず 承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. 承認された効果・効能以外の効果・効能について | 【禁止】承認されている効能・効果以外の効能・効果を実際に有している場合でも、未承認のもの ※追加申請した際に、その効果・効能が承認される場合でも、同等の扱いである。 |
| 2. 未承認等の効果・効能等の表現について | 【禁止】 未承認の効果・効能の表現に関して、薬理学的に医薬品等の作用と関係あるもの 【禁止】 薬理学的に医薬品等の作用と認められないもの ※薬理学=薬物を投与したときに生体に起こる変化を研究する学問) |
| 3. 効果・効能の副次的効果の表現について | 【禁止】 効果・効果の2次的三次的効果等の表現 |
| 4. 効果・効能のしばりの表現について | 《注意喚起》 承認された効果・効能に「しばり表現」が付されている医薬品等の広告を行う場合、省略することなく、正確に付記・付言する 《注意喚起》 テレビ・ラジオにおける効能・効果等のしばり表現は、漢方製剤に限り省略可能だが、注意喚起の旨を付記または付言する |
| 5. 同系統の数種の医薬品等を単一の広告文で広告する場合 | 《注意喚起》 効果・効能の表現は、同系統の数種の医薬品等に共通する効果・効能でなければならない。 |
| 6. 医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器または再生医療等製品の同一紙面での広告について | 【禁止】 同一紙面またはテレビ等で同時に広告を行う際の「相乗効果を得るような誤解を招く広告」または「科学的根拠に基づかず併用を促すような広告」 ※医薬品及び指定医薬部外品に限る |
| 7. 個々の成分の効果・効能について | 【禁止】 数種の成分からなる医薬品等について、下記のケースを説明する場合は、医薬品等の承認が成されている効果・効能の範囲内のみ 1. 「個別の成分についての効果・効能の説明を行う場合」 2. 「医薬品等の作用機序を説明する場合」 【禁止】 「漢方薬」または「漢方製剤」の効果の表記 |
| 8. 複数の効果・効能を有する医薬品等の広告について | 《注意喚起》「〇〇剤」という表現:薬効分類として認められ、分類が適当である場合は表記可能(例:「解熱鎮痛消炎剤」) 《注意喚起》「〇〇専門薬」という表現:承認を受けた名称である場合以外は表記不可(NG例:「胃腸病の専門薬」「皮膚病の専門薬」) |
3. 効能・効果や性能及び安全性についての表現
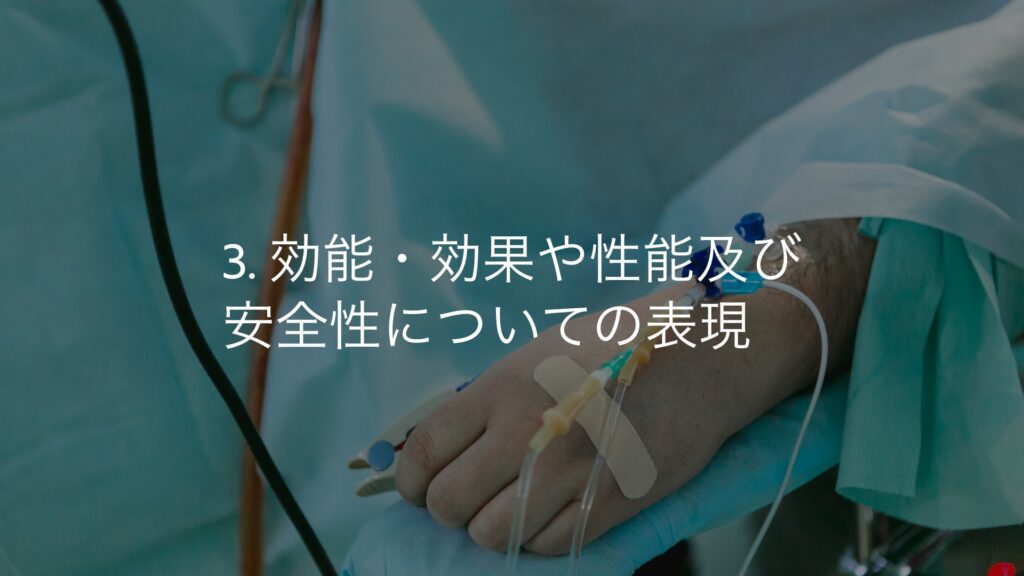
医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「効果・効能や性能、安全性についての表現」について、次のように規制しています。
(3)医薬品等の成分等及び医療機器の原材料等についての表現の範囲
医薬品等の成分及びその分量又は本質等並びに医療機器の原材料、形状、構造及び原理について、承認書等への記載の有無にかかわらず、虚偽の表現、不正確な表現等を用い効能効果等又は安全性について事実に反す る認識を得させるおそれのある広告をしてはならない。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. 成分について | 【禁止】医薬品等の成分及びその分量または本質等並びに医療機器の原材料、形状、 構造及び原理について、単味であるものを総合、複合等とすること (例:「高貴薬配合」「デラックス処方」) |
| 2. 特定成分の未配合表現について | 《注意喚起》 特定の薬物(カフェイン・ナトリウム・ステロイド・抗ヒスタミン等) を配合していない旨の広告は、下記に留意することで可能 ・他社誹謗や安全性の強調の禁止・理由を併記する・2次的効果を訴えない |
| 3. 配合成分の表現について | 《注意喚起》 配合されている成分名を具体的にすべて列挙する (例:「各種‥」「数種‥」) 【禁止】配合成分数は事実である限り表示可能だが、強調表現は禁止である (例:「10種のビタミン‥」「15種の制約を配合‥」) 《注意喚起》配合成分中の特定成分を取り出して表現する場合、有効成分かつ承認された効果・効能等と関連がある場合、表示可能 |
| 4. 原産国の表現について | 《注意喚起》「製品を輸入して販売する場合」または「バルクを輸入して国内で小分け製造する場合」、原産国の表記可能(例:「スイス生まれの〇〇」「イギリス製〇〇」「ドイツ生薬〇〇」「イギリス製」) 《注意喚起》原料を輸入し、国内で製造した場合、正確に記載する(例「〇〇から原料を輸入し、製造した」) |
| 5. 安全性関係について | 【禁止】安全性関係の表記 (例:「天然成分を使用しているので副作用がない」「誤操作の心配 のない安全設計」) |
| 6. 配合成分の略記号表示 | 【禁止】配合成分の略記号表示《アルファベット等の略号・記号等》 |
4. 用法・用量についての表現
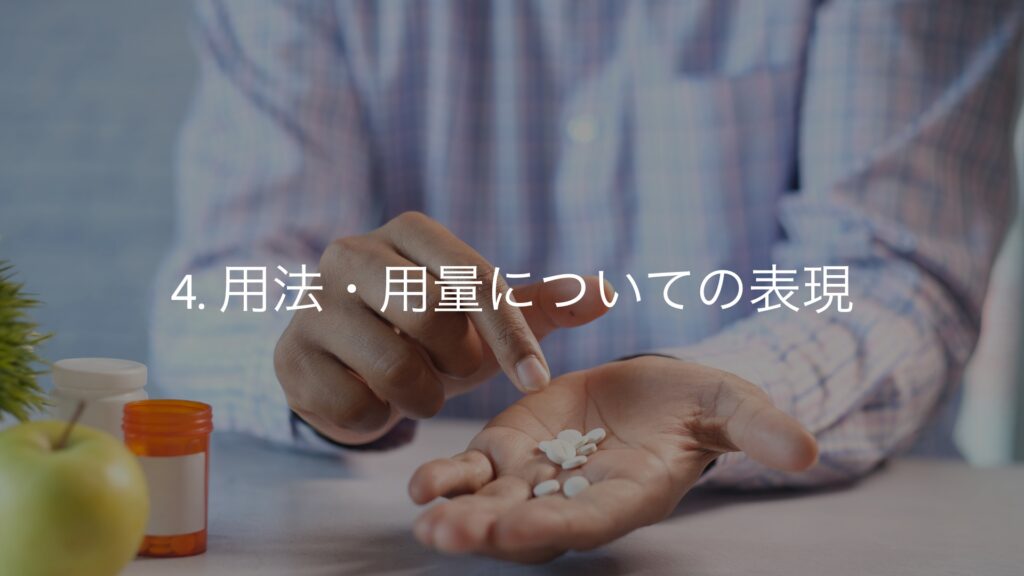
医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「用法・用量についての表現」について、次のように規制しています。
(4)用法用量についての表現の範囲
医薬品等の用法用量について、承認等を要する医薬品等にあっては承 認等を受けた範囲を、承認等を要しない医薬品等にあっては医学、薬学 上認められている範囲をこえた表現、不正確な表現等を用いて効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告を してはならない。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. 併用に関する表現について | 【禁止】併用に関する表現 |
| 2. 安全性に関する表現について | 【禁止】「いくら飲んでも副作用がない」「使用法を問わず安全である」等の表現 |
| 3. 複数の用法用量がある場合の表現について | 【禁止】複数の用法・用量がある場合において、「1つの用法・用量のみ」または「特定の用法・用量のみ」を強調すること |
5. 効果・効能または安全性を保証する表現の禁止

医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「効果・効能または安全性を保証する表現の禁止」を次のように規制しています。
(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安 全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはなら ない。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. 効果・効能等または安全性の保証表現について | 【禁止】疾病の要因・患者の性別・年齢等を問わず効果・効能が確実かつ安全であることを保証するような表現 (例:「根治」「全快する」「安全性は確認済み」「副作用の心配はない」) |
| 2. 歴史的な表現について | 《注意喚起》企業の歴史の事実として創業年数や商品の販売年数を表記することは可能 【禁止】企業または医薬品等の歴史に関連させ「安全性・優秀性の保証となる表現」や「他社に対する優越性の保証となる表現」 |
| 3. 臨床データ等の例示について | 【禁止】一般向けの広告で「臨床データ」や「実験例」等を例示すること |
| 4. 図面・写真等について | 【禁止】使用前後に関わらず、図面・写真等による、下記の表現の禁止 1. 承認等外の効果・効能等を想起させるもの 2. 効果発現までの時間及び効果持続時間の証となるもの 3. 安全性の保証表現となるもの |
| 5. 使用体験談等について | 【禁止】愛用者の感謝状・感謝の言葉等の例・「私も使っています。」等使用経験または体験談的広告 ただし、下記のケースで、過度な表現や保証的な表現を除き可能 1. 「目薬」「外皮用剤」」「化粧品」等の広告で使用感を説明する場合(使用感のみを強調する広告はNG) 2. タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合 |
| 6. 身体への浸透シーン等について | 《注意喚起》 アニメーション・模型などを用いて表現する場合、「効果・効能等」または「安全性に関する虚偽」または「誇大な表現」とならないよう十分に注意する |
| 7. 疾病部分の炎症等が消える場面の表現について | 《注意喚起》テレビ広告・ウェブサイト等で用いる、画面中の模式図・アニメーショ ン等については、効果・効能の保証的表現とならないよう留意する |
| 8. 副作用等の表現について | 【禁止】「副作用が少ない」「比較的安心して」「刺激が少ない」等の表現 《注意喚起》低刺激性等が立証されており、安全性を強調しない場合: 「眠くなりにくい」と表現することは、その製剤として科学的根拠があり安全性の保証につながらない場合、表記可能 |
| 9.「すぐれたききめ」「よくききます」の表現について | 【禁止】下記の強調表現の使用 1. キャッチフレーズ:人の注意を引くように工夫した印象的な宣伝文句(例:「よくきく〇〇」「〇〇はよくきく」) 2. 文字:他の文字と比較して大きい・色が濃い(淡い)・色が異なる・文字の上に点を打つ 3. 音声:大きく発音する・一音ずつ区切って発音・「よーく」と強く伸ばす 4. 文字&音声:「すぐれた」と「よくききます」を重ねて表現 |
| 10.「世界〇〇ヵ国で使用されている」旨の表現について | 【禁止】効果・効能等が確実であることまたは安全であることを保証するような表現 《注意喚起》単に事実のみを表現する場合は表記可能 |
6. 効果・効能または安全性についての最大級の表現またはこれに類する表現の禁止

医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「効果・効能または安全性についての最大級の表現またはこれに類する表現の禁止」を次のように定めています。
(6)効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現の禁止
医薬品等の効能効果等又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現をしてはならない。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. 最大級の表現について | 【禁止】「最高のききめ」「無類のききめ」「〇〇薬の王様」「〇〇薬のエース」「世界一を誇る〇〇」「売上げNo1*」 ※新指定医薬部外品以外の医薬部外品及び化粧品を除く |
| 2. 新発売等の表現について | 《注意喚起》「新発売」「新しい」等の表現は、発売後12ヵ月間を目安に使用する |
| 3. 「強力」「強い」の表現について | 【禁止】「強力な〇〇」「強い〇〇」 |
| 4. 安全性の表現について | 【禁止】「比類なき安全性」「絶対安全」などの最大級の表現 |
7. 効能効果の発現程度についての表現の範囲
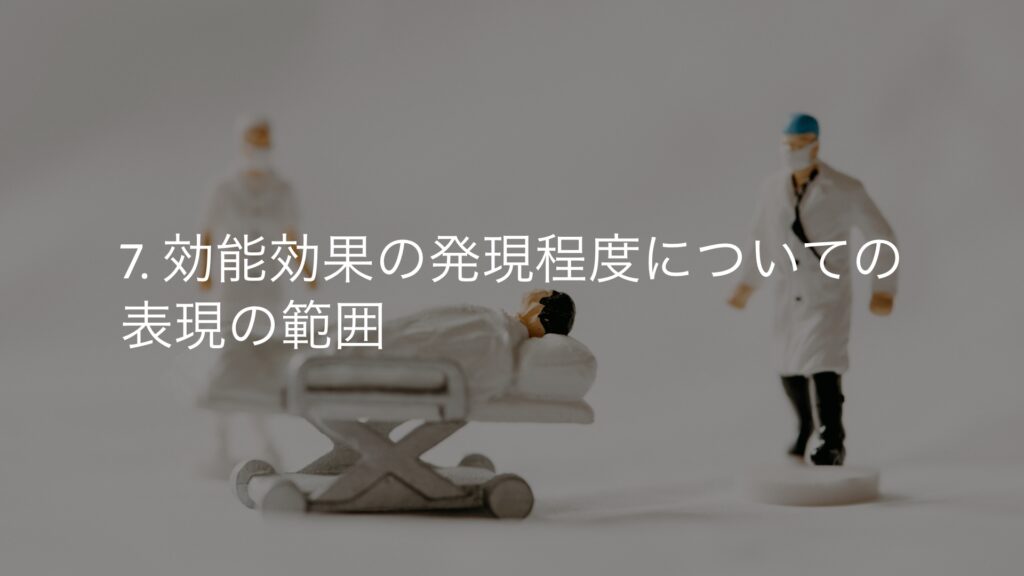
医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「効果・効能の発言程度についての表現の範囲」を次のように定めています。
(7)効能効果の発現程度についての表現の範囲
医薬品等の速効性、持続性等についての表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならない。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. 効能効果等の発現程度について | 【禁止】「すぐ効く」「飲めばききめが3日は続く」等の表現 |
| 2. 速効性に関する表現について | 【禁止】「速く効く」「顆粒だから速く溶け効く」表現 《注意喚起》速効性について、承認等された効果・効能、用法用量等の範囲内で、医学、 薬学上十分証明されたものについて: (例:「解熱鎮痛消炎剤」「局所麻酔剤を含有する歯痛剤(外用)」「抗 ヒスタミン薬を含有する鎮痒消炎薬(外用)」「浣腸薬」) ・強調表現: ヘッドコピー・キャッチフレーズとして使用する場合「早く」という言葉を1回の広告中原則として2回以上使用する場合 ・剤型等の比較:「液剤だから早く効く」等の表現 ・使用前・使用後的表現:作用時間を明示または暗示するもの: (例:「新幹線の大阪で痛んで京都で治っている」) |
| 3. 持続性に関する表現について | 【禁止】「効力持続型」等の表現:承認等された効果・効能、用量・用法等の範囲内で、医学・薬学上十分に証明された場合以外の表記 |
8. 本来の効果・効能等と認められない表現の禁止
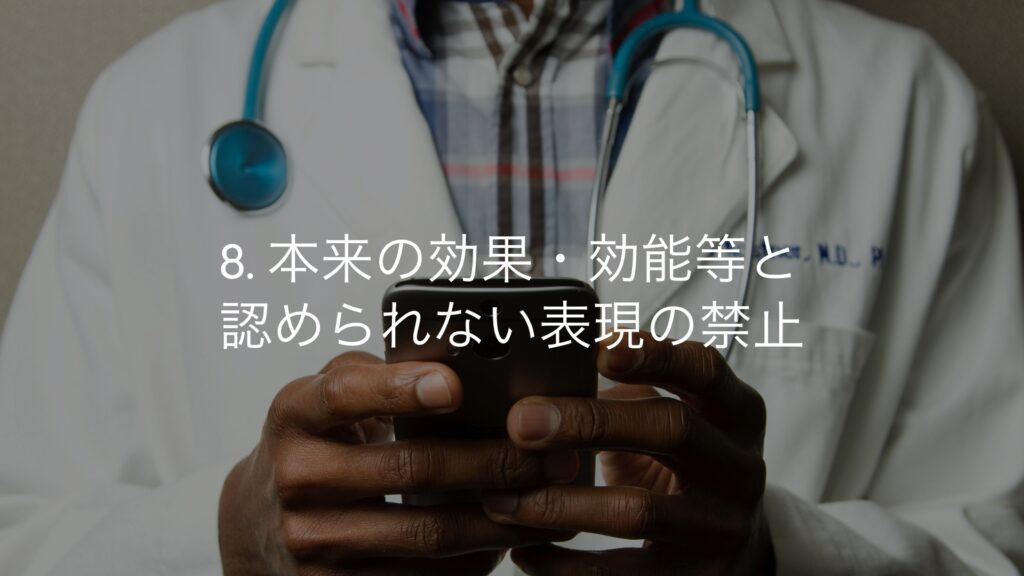
医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「本来の効果・効能等と認められない表現の禁止」を次のように規定しています。
(8)本来の効能効果等と認められない表現の禁止
医薬品等の効能効果等について本来の効能効果等とは認められない効果・効能等を表現することにより、その効能効果等を誤認させるおそれの ある広告を行ってはならない。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. 本来の効果・効能以外の表現について | 【禁止】本来の効能効果等とは認められない表現 (例:頭痛薬→「受験合格」) (例:ホルモン剤や保険薬→「夜を楽しむ」「迫力を生む」「活力を生み出す」、「人生を2倍楽しむ」) |
| 2. 未承認の効能効果等の表現について | 『違反内容』 ■ 薬理学的に当該医薬品等の作用と関係あるもの:第4の3「承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲」に違反 ■ 直接、薬理学的に当該医薬品の作用とは認められないもの:本項に違反 |
| 3. 本基準の他の項目との関連について | 『薬機法に接触する恐れのある項目』 ■ 効果・効能等の二次的・三次的効果の表現: 第4の3(1)「承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲」 ■ 本項に抵触する表現: 第4の4「過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限」 第4の14「医薬品の化粧品的若しく は食品的用法又は医療機器の美容器具的若しくは健康器具的用法につい ての表現の制限」 ■ 性的表現: 第3 広告を行う者の責務 |
9. 過量消費または乱用助長を促すおそれのある広告の制限

医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「過量消費または乱用助長を促す恐れのある広告の制限」について、次のように規定しています。
4 過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限
医薬品等について過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告を行ってはならない。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. 子どものテレビ広告等への使用について | 【禁止】小学生以下の子どもをモデルとして広告に使用する場合: 1. 殺虫剤:幼少児を使用しない 2. 子どもが自分で医薬品を手に持つまたは使用する場面を用いること |
| 2. 服用・使用場面の広告表現について | 《注意喚起》服用・使用場面を広告で行う場合: 乱用助長に繋がらないよう注意する 【禁止】内服剤:定められた用法用量を明瞭に表現する |
10. 一般向広告における効果・効能についての表現の制限

医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「一般向け広告における効果・効能についての制限」について、次のように規定しています。
6 一般向広告における効能効果についての表現の制限
医師又は歯科医師の診断若しくは治療によらなければ一般的に治癒が期待 できない疾患について、医師又は歯科医師の診断若しくは治療によることな く治癒ができるかの表現は、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告に使 用してはならない。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. 医師等の治療によらなければ治癒等が期待できない疾患について | 『注意事項』医師または歯科医師の診断もしくは治療がない場合、一般的に治癒が期待できない疾患は下記を指す: 「胃潰瘍」「十二指腸潰瘍」「糖尿病」「高血圧」 「低血圧」「心臓病」「肝炎」「白内障」「性病」 ※一般大衆が自己の判断で使用した場合、保健衛生上重大な結果を招くおそれのある疾病 |
| 2. 上記疾病名の記載について | 【禁止】 疾病名を記載するだけであっても、自己治癒を期待させるおそれがあるため、上記の疾病名の広告の使用 |
11. 使用及び取扱い上の注意について医薬品等の広告に付記または付言すべき事項
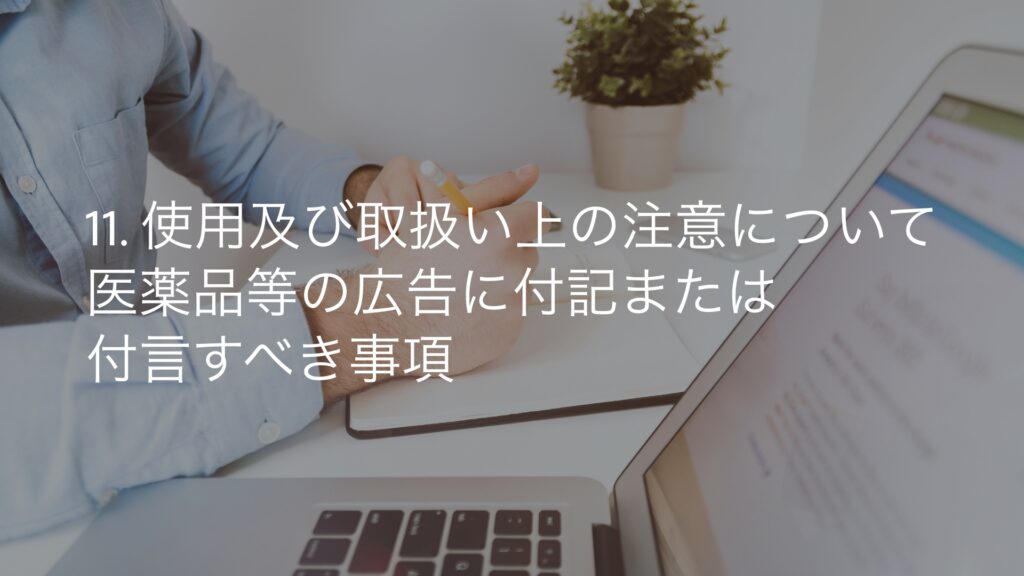
医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「使用及び取扱い上の注意について医薬品等の広告に付記または付言すべき事項」について、次のように規定しています。
8 使用及び取扱い上の注意について医薬品等の広告に付記し、又は付言すべき事項
使用及び取扱い上の注意を特に換起する必要のある医薬品等について広告 する場合は、それらの事項を、又は使用及び取扱い上の注意に留意すべき旨 を、付記し又は付言しなければならない。 ただし、看板等の工作物で商品名のみを広告する場合はこの限りではない。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. 使用上の注意等の付記又は付言について | 《注意喚起》使用または取扱い上の注意を特に喚起する必要のある医薬品は、添付文章等にその旨を記載する 《注意喚起》広告においても、 それらの事項または使用及び取扱い上の注意に留意すべき旨を付記また付言する |
12. 他社の製品の誹謗広告の制限
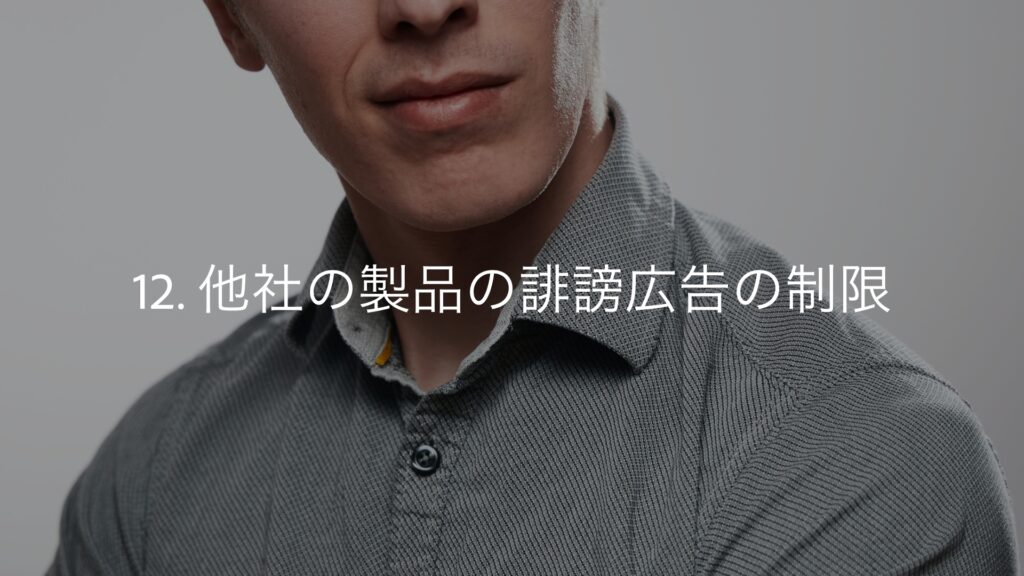
医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「他社の製品の誹謗広告の制限」について、次のように規定しています。
9 他社の製品の誹謗広告の制限
医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. 誹謗広告について | 【禁止】他社の製品の品質等について実際のものより悪く表現すること: (例:「他社の口紅は流行遅れのものばかり」) 【禁止】他社の製品の内容について事実を表現すること: (例:「〇〇社は、どこでもまだ〇〇式製造だ」 ) |
| 2. 「比較広告」について | 【禁止】漠然と比較するケース 【禁止】明示的・暗示的を問わず他社製品との比較広告: ※製品同士の比較広告を行う場合は、自社製品の範囲かつその対照製品の名称を明示する場合に限る |
13. 医薬関係者等の推せん
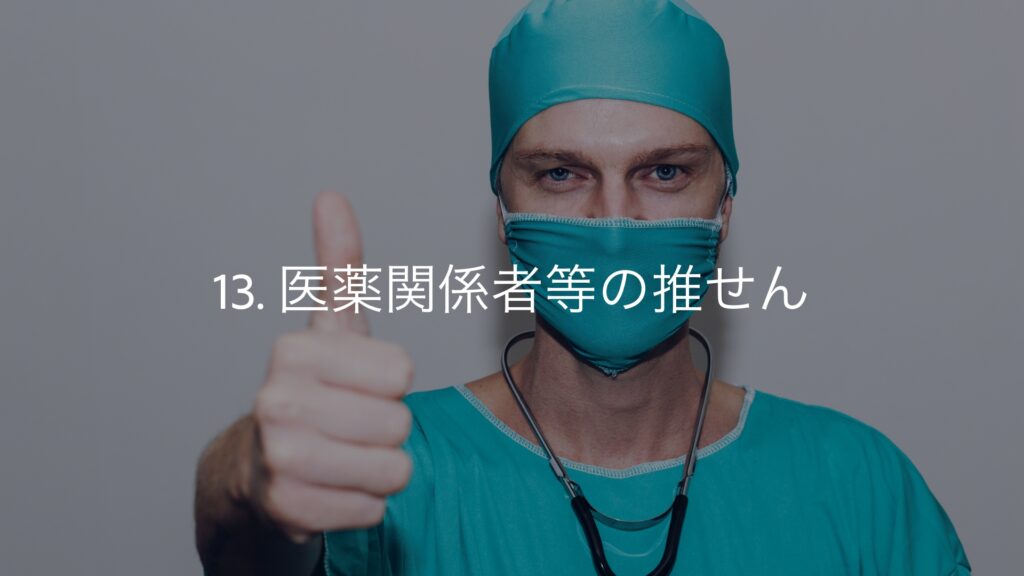
医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「医薬関係者等の推せん」について、次のように規定しています。
10 医薬関係者等の推せん
医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を 含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告 を行ってはならない。 ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. 医薬関係者の推せんについて | 【禁止】事実である場合も、医薬品等の推せん広告等は不適当である ※「公認」:法による承認及び許可等も含まれる※「特別の場合」:市町村がそ族昆虫駆除事業を行うに際し、特定の殺虫剤等の使用を住民に推せんする場合のみ |
| 2. 推せん等の行為が事実でない場合について | 『薬機法に接触する恐れのある項目』:推せん等の行為が事実でない場合 |
| 3. 特許について | 『薬機法に接触する恐れのある項目』:特許について ※事実でない場合は虚偽広告として取り扱う |
| 4.「公務所・学校・学会を含む団体」の範囲について | 《注意喚起》「公務所・学校・学会を含む団体」の範囲は、厳格な意味の医薬関係に 限定されない |
| 5. 厚生労働省認可(許可・承認等)等の表現について | 『薬機法に接触する恐れのある項目』:厚生労働省認可(許可・承認等)経済産業省認可(許可)等の表現 |
14. 懸賞・賞品等による広告の制限

医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「懸賞・賞品等」について、次のように規定しています。
11 懸賞、賞品等による広告の制限
(1)過剰な懸賞、賞品等射こう心を煽る方法による医薬品等又は企業の広告を行ってはならない。
(2)懸賞、賞品として医薬品を授与する旨の広告を行ってはならない。 ただし、家庭薬を見本に提供する程度であればこの限りではない。
(3)医薬品等の容器、被包等と引換えに医薬品を授与する旨の広告を行ってはならない。
※(2)は医薬品に限定しているため、省略いたします。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. 懸賞・賞品等による広告の制限 | 【禁止】過剰な懸賞・賞品等、射こう心を煽る方法による医薬品等または企業の広告 【禁止】医薬品等の容器・被包等と引き換えに医薬品を授与する旨の広告 |
15. 不快・迷惑・不安・恐怖を与える恐れのある広告の制限
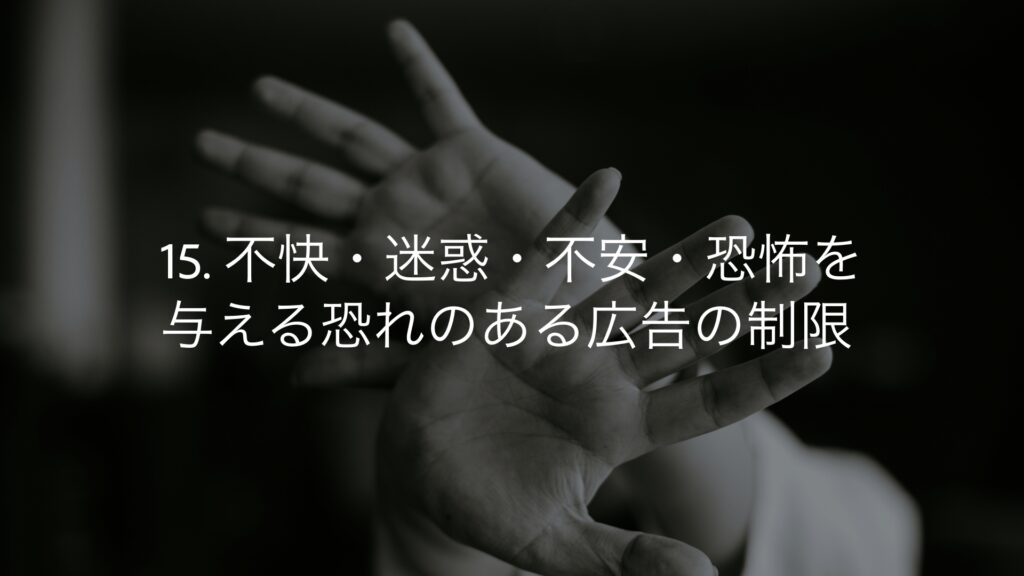
医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「不快・迷惑・不安・恐怖を与える恐れのある広告の制限」について、次のように規定しています。
12 不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある広告の制限
広告に接した者に、不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある表現 や方法を用いた広告を行ってはならない。 特に、電子メールによる広告を行う際は、次の方法によらなければならな い。
(1)医薬品販売業者の電子メールアドレス等の連絡先を表示すること。
(2)消費者の請求又は承諾を得ずに一方的に電子メールにより広告を送る 場合、メールの件名欄に広告である旨を表示すること。
(3)消費者が、今後電子メールによる広告の受け取りを希望しない場合、 その旨の意思を表示するための方法を表示するとともに、意思表示を示 した者に対しては、電子メールによる広告の提供を行ってはならないこと。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. 不快・迷惑・不安・恐怖を与える恐れのある広告の制限 | 【禁止】広告に接した者に、〈不快・迷惑・不安・恐怖〉を与えるおそれのある表現や方法を用いた広告 《注意喚起》 1. 電子メールによる広告を行う場合: 医薬品販売業者の電子メールアドレス等の連絡先を表示する 2. 消費者の請求または承諾を得ずに一方的に電子メールにより広告を送る場合: メールの件名欄に広告である旨を表示する 3. 消費者が、今後電子メールによる広告の受け取りを希望しない場合: その旨の意思を表示するための方法を表示する 意思表示を示した者に対しては、電子メールによる広告の提供を行ってはならない |
16. テレビ・ラジオの提供番組等における広告の取り扱い
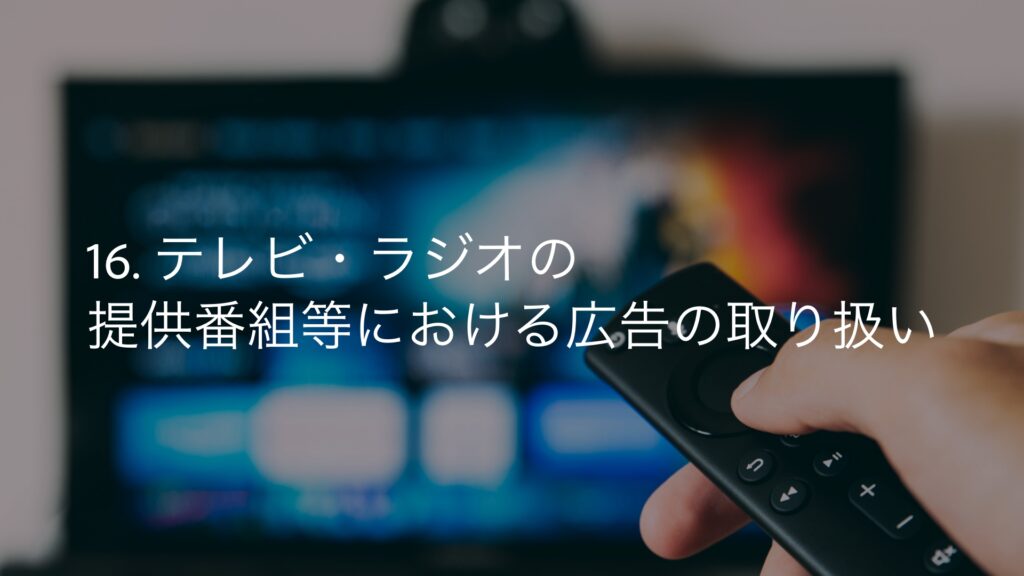
医薬品等適正広告基準では、再生医療等製品をはじめ、薬機法に係る製品の「テレビ・ラジオの提供番組等における広告の取り扱い」について、次のように規定しています。
13 テレビ、ラジオの提供番組等における広告の取扱い
(1)テレビ、ラジオの提供番組又は映画演劇等において出演者が特定の医薬品等の品質、効能効果等、安全性その他について言及し、又は暗示する行為をしてはならない。
(2)テレビ、ラジオの子ども向け提供番組における広告については、医薬品等について誤った認識を与えないよう特に注意しなければならない。
| 規制項目 | 具体的な内容 |
| 1. テレビ・ラジオの提供番組等における広告の取り扱い | 【禁止】テレビ・ラジオなどの提供番組または映画演劇等: 出演者が特定の医薬品等の〈品質、効果・効能、安全性、その他〉について言及・明示する行為 《注意喚起》テレビ・ラジオの子ども向け提供番組における広告: 医薬品等について誤った認識を与えないようにする |
薬機法に違反した場合の罰則

冒頭にご紹介した通り、薬機法に違反した場合、次の処遇を受ける可能性があります。
- 行政処分
- 課徴金納付命令
- 刑事罰
上記の違反行為について、簡単にまとめると次の図の通りです。
| 項目 | 詳しい内容 |
| 行政指導 | 行政処分には次のような段階を設けています。 《行政処分までの流れ》 1. 行政処分 2. 業務改善命令 3. 措置命令 4. 業務停止命令 5. 許可・登録の取消 6. ★課徴金納付命令 |
| 課徴金納付命令 | ■ 第66条の「虚偽・誇大広告等の禁止」に違反した場合 支払い金額:虚偽・誇大広告を行っていた期間中に得られた売上金額の4.5% 支払い期間は:違反行為の開始日から数えて、最長で3年間 |
| 刑事罰 | ■ 第84条:無許可製造・販売:3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または両方 ■ 第85条:虚偽・誇大広告:2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、または両方 ■ 第86条:特定疾病用の医薬品等に関する広告:1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、または両方 |
薬機法に違反した場合、特に、薬機法が改正され、課徴金制度の導入以降は、違反対象商品の売上の4.5%の支払い義務が課せられることになりました。
例えば、10億円の売り上げ金額が生じた場合には4,500万円、1億円の場合には450万円と、大きな額の課徴金を支払う必要があります。
当該製品を広告した企業の社員から消費者まで多岐にわたって、多大な影響を及ぼす可能性があることから、薬機法について正しい知識を学び、専門家のアドバイスを取り入れるなどして、消費者が安心して、当該製品を使用できるよう努めることが大切ではないでしょうか。
各違反行為の詳細については、こちらの記事をご覧ください。
薬機法(旧薬事法)に違反しないためには専門家の力を借りること

ここまで、「薬機法に関する前提知識」をはじめ、薬機法における「再生医療等製品の定義や種類、再生医療等実施の流れ」などの概要に加え、「薬機法の違反行為」、「違反行為の一つで、今回のメインテーマである広告違反について」、「再生医療等製品にまつわる広告における注意事項」「違反した場合の罰則」など、薬機法における再生医療等製品を取り巻く広告規制について解説させていただきました。
繰り返しとなりますが、薬機法における再生医療等製品の定義とは次の通りです。
特に、再生医療等製品を含む、薬機法の該当製品を扱う際には、日々情報をアップデートし、薬機法を遵守するよう心掛ける必要があります。
薬機法に違反した場合、行政処分・課徴金納付命令・刑事罰の対象になる可能性があるため、一人ひとりが薬機法について学び、ルールを遵守するよう努めることが重要です。
ただし、薬機法等のリーガルチェックや専門性の高い訴求表現を行うことは、多くの規約が設けられていることから、どれだけ確認をしても、不安が残ってしまう方も少なくないのではないでしょうか。
弁護士をはじめとする法律の専門家に依頼することで、不正確な情報の発信やトラブルを未然に防げるだけでなく、製品を使用する消費者の安全を守ることにも繋がります。
再生医療等製品における広告規制に関する助言や審査、薬機法についてご不明点がある場合には、XP法律事務所までお気軽にご相談ください。
お問い合わせ先
【XP法律事務所】
- 代表弁護士:今井 健仁(第二東京弁護士会)
- 所在地:〒104-0061 中央区銀座1-15-4 銀座一丁目ビル13階
- TEL:03-6274-6709(銀座本店)
- FAX:03-6274-6710(銀座本店)
- ホームページ:https://xp-law.com/
